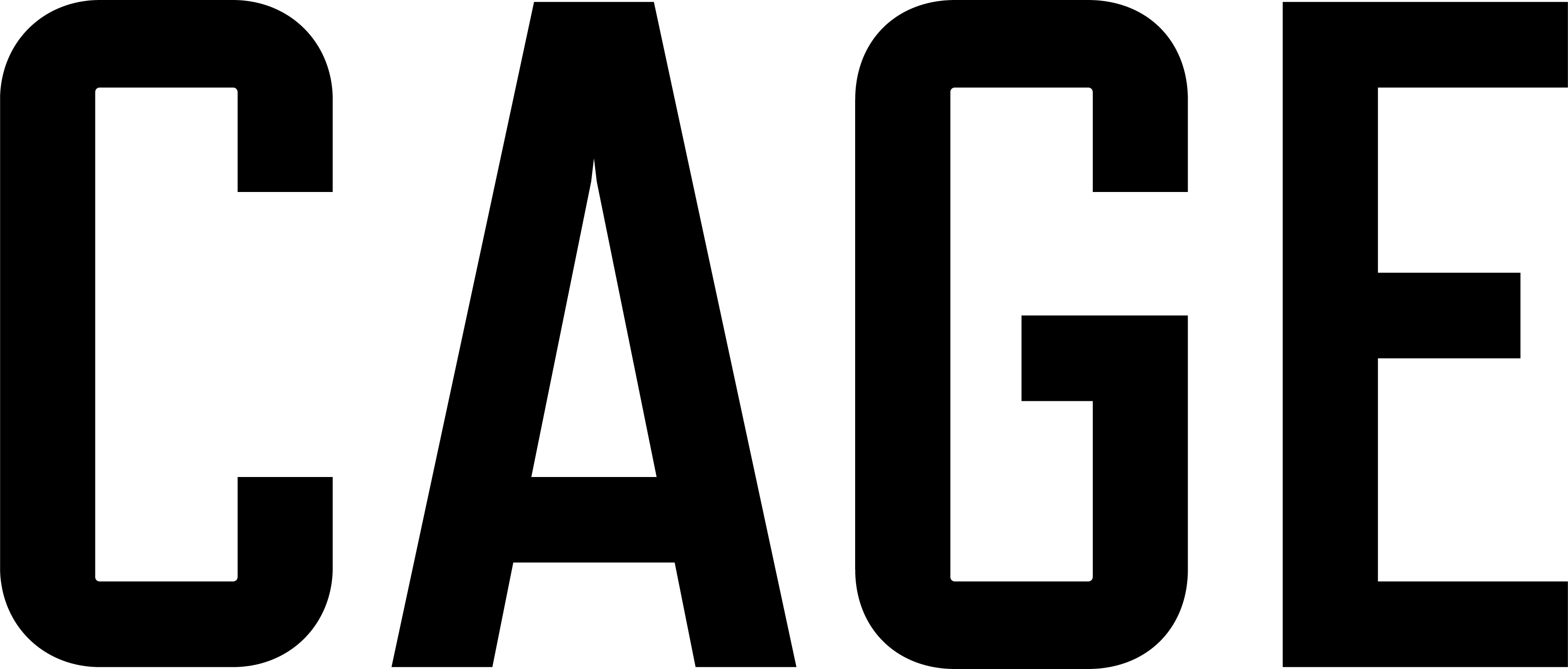MOVIE丨2025.04.13
観客を楽しませながら不安にさせる… スリリングで残酷、不気味でクセになる 万人向けではないポン・ジュノ監督らしいSF作『ミッキー17』

© 2025 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved.
誰でも一度は「自分は代わりがきく存在かも」と思ったことがあるだろう。しかし『ミッキー17』が描くのは、もっと残酷。「人間が使い捨てにされる」話だ。ポン・ジュノ監督はこのコンセプトを、企業社会の風刺、そしてフィリップ・K・ディック的な偏執的SFに広げてみせた。
舞台は2054年、物語の主人公ミッキー・バーンズ(演:ロバート・パティンソン)は「エクスペンダブル=消耗品」。地球に借金を残した彼は、死ぬたびに再生されるという過酷な任務に志願する。任務はシンプルで、必要に応じて死ぬこと。そしてすぐに「複製」として新たに印刷され、記憶も引き継いでまた働かされる。舞台は氷に覆われた惑星ニヴルヘイム。ミッキーたちは効率化がすべての植民地計画の中で、危険で汚れ仕事を担う存在として扱われている。
死ねば、すぐ次が印刷される。もちろん記憶もそのままだ。ただし、いくら繰り返しても「死」の恐怖が消えることはない。この設定だけで背筋が寒くならなくても、ポン・ジュノの手腕でじわじわと恐怖は滲み出してくる。ブラックユーモアと内省的な静けさの合間に、ぞっとする気配が忍び込んでくる。ミッキーが印刷機からガクガクと吐き出され、毎回冷酷に拷問され、実験されるシーンを見れば、それだけで十分だ。
パティンソンの演技は、あえて“冴えない男”としての魅力を全面に出している。気味の悪い話し方で、美形俳優のイメージを抑え、何度も殺されても必死に生き延びようとする姿を見せる。奇妙で悲しみに満ちており、滑稽さと絶望のあいだで揺れながら、“無価値な歯車”として冷たいシステムの中を彷徨う。彼の皮肉、ため息、小さな反抗。それらは大企業の中では無意味だ。そんな彼の奮闘に、次第に観客は応援せざるを得なくなってくるから不思議だ。それは自分自身を重ねているかもしれないからだ。
植民地計画を進めるコロニーのリーダーは、落選した元大統領候補で、演じるマーク・ラファロは見る者を不安にさせるほどの迫力。彼は独裁的で恐怖と混乱で人を支配する、某大統領のようなキャラクターだ。ミッキーとリーダーの対立は、単なるサバイバルの話じゃない。独裁と個の自由の衝突でもある。
そしてミッキーが死ぬことを拒否した時から事件は起こる。物語は急加速、ニヴルヘイムに住む先住異星人たちを巻き込んで怒涛のサバイバル・スリラーへと変貌する。本作は資本主義の矛盾、労働の搾取、アイデンティティの本質がテーマだ。ミッキーの飄々としたキャラクターとユーモアに紛れて、いつの間にか観る側に入り込んでくる。そして、笑ってるうちに、とんでもなく残酷な話に気づかされる瞬間がくる。
『ミッキー17』は「パラサイト」のような現代的な美学は抑えめで、むしろ閉塞感と奇妙さが支配する。しかし、その中に、ユーモアと自由さ、そしてポン・ジュノならではの知性が詰まっている。観客を楽しませながら、しっかりと不安にさせる。正直、万人向けではないが、作品全体にアイデアが満ちている。スリリングで、考えさせられ、どこか不気味でクセになる物語。ポン・ジュノはまたひとつ、鑑賞後もずっと頭から離れない作品を生み出した。