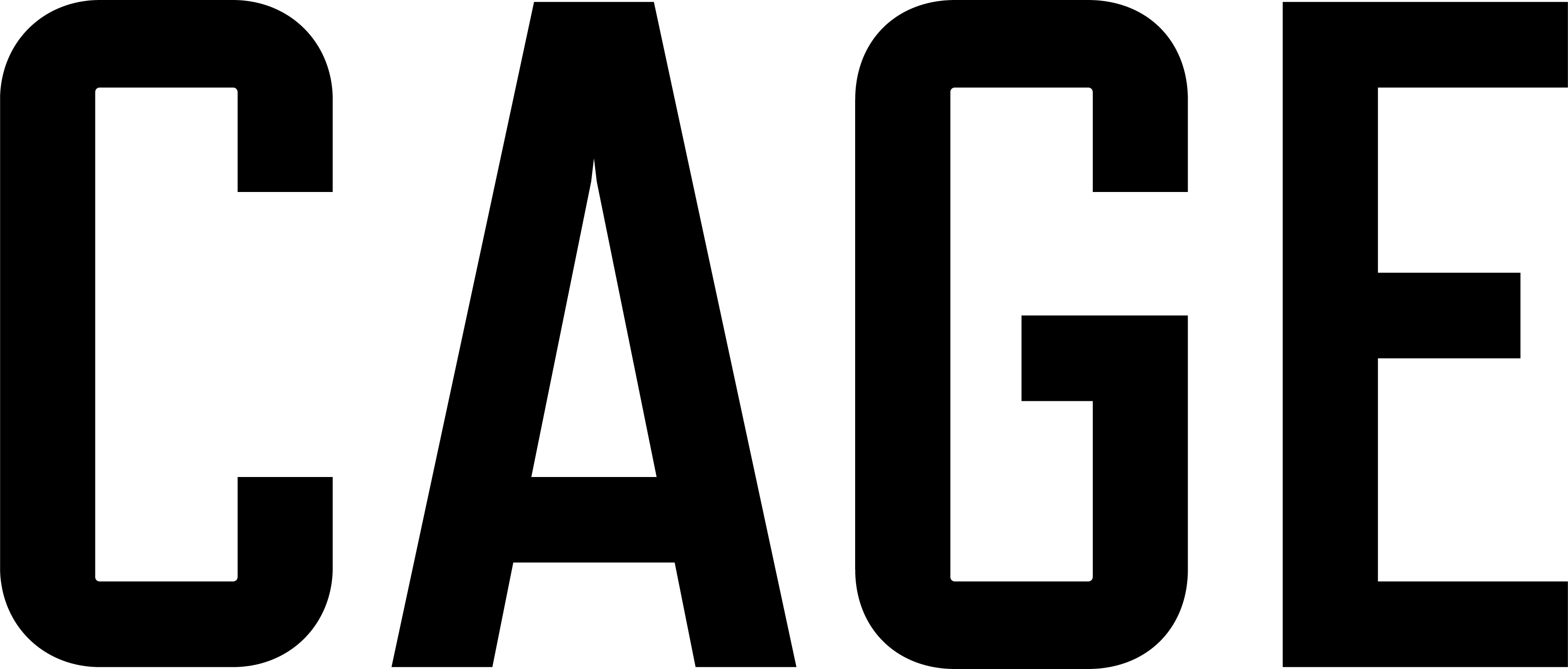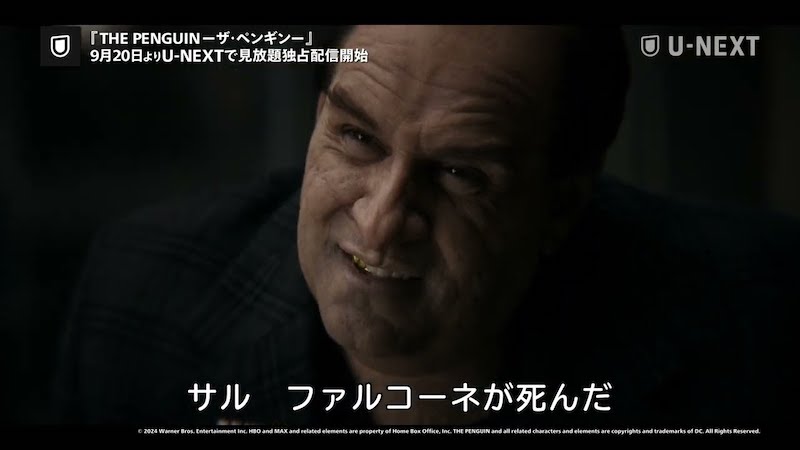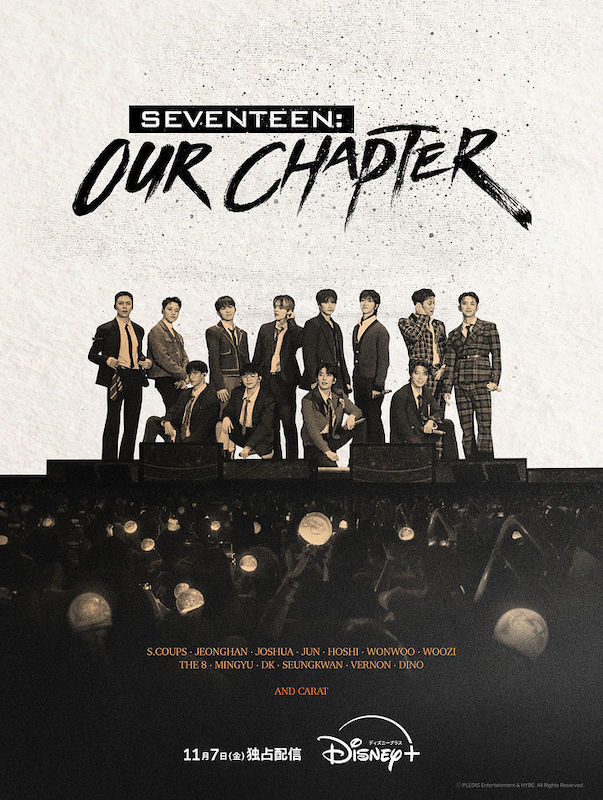STREAMING丨2025.07.05
「科学的な手法で消費者を騙している」 そのクリックは罠だらけ… ネット販売に潜む“見えない消費コントロール”

今や多くの国民が、大手通販サイトAmazonをはじめ、様々な形で通販サイトを利用している。しかし、我々がそうした通販サイトを利用している場面のうち、“本当に欲しくて購入”している回数は、一体どのくらいなのだろうか? 「購入」というものに対し、これまでと違った視点が持てるドキュメンタリーが『今すぐ購入: 購買意欲はこうして操られる』(Netflix)だ。
本作は冒頭に登場するAmazonの元女性スタッフが口にする「科学的な手法で消費者を騙している」という、ある意味、センセーショナルな言葉が示すように、我々の消費行動が、売り手側によって操作・誘導されるという危険性について踏み込んだドキュメンタリーだ。常日頃、我々は多くの場合において、自身の「買い物」について、自らの欲求や必要性に応じて、自分の意思決定で行っていると思われがちだが、その実、“プロ”に言わせれば、我々一般消費者の心理やその結果生み出される行動などについて、科学的な分析が徹底して行われ、それに基づいたサイト構成や画面遷移、プロモーションや各種演出などを盛り込むことで、「ついつい買ってしまう」レベルを超えた消費を作為的に発生させることができるのだという。「1クリック購入」のボタンも、「~円以上で送料無料」というリンクも、そうした彼らの“トラップ”の例だ。
こうした顧客の心理に訴える手法だけでは、多くの企業が狙う「売上げの最大限化」はなしえない。そこで彼らが次のステップとして着手するのは、消費者側が何らかの切迫感にも似た想いで、“再考の暇なく”商品を購入し続けるという行動パターンだ。こうした行動パターンを生み出すもののうち、比較的“平和”なものは、メーカー側のアイコンともいえる有名人の広告起用や、彼らによるメッセージの発信であったり、トレンドや季節性イベントを過剰に盛り上げる大々的なプロモーションなどであったりするのだが、それよりも最もシンプルで低コストで実現できるのは、「計画的陳腐化」と呼ばれる手法。これは、「すぐに使い物にならなくなる商品を売る」という、消費者側からすると悪辣極まりないものなのだが、売り手であるメーカー側は、あえて製品の寿命を短くし、それを買い手側である消費者側が自前で修理することをできなくすること、そしてそれが壊れるタイミングで新商品をセンセーショナルな形で市場に投下することで、消費者は知らず知らずのうちに、売り手側によって買うタイミングをコントロールされた状態に陥ってしまうのだ。Facetimeの開発に携わったという元・アップルのエンジニアが「毎日約1300万台もの電話が捨てられている。信じられない数字だよ。全員が2~3年おきに買い替えてる。高価な代物なのにだよ。文明が持つ技術の結晶とも言える製品が使い捨てにされている。その数字を見てわかったよ。どこをどう見てもこれは歪んでいると」と語るように、本来であれば簡単に壊れるはずのないものが計画的に壊されることで、我々現代人は異常に速いサイクルで新商品を購入するという状況となっているのである。
こうした“異常に速い購入サイクル”が、大量廃棄や環境破壊に繋がるのは言うまでもないが、そうした消費者側の後ろめたさを軽減する狙いで、売り手である企業側は、リサイクル可能な製品のリリースを投入したり、企業全体として環境保全に尽力しているかのような体をとりがちなのだという。実際にはメーカーを通じて回収された製品が、リサイクルされずにそのまま廃棄されているというケースも少なくないのだそうだ。つまり、企業側の“環境に対する取り組み”の多くが、消費者に購入を促すために設定された“演出”でしかないわけだ。このドキュメンタリーが浮き彫りにした“売り手側のスタンス”を象徴するかのように、前出のAmazonの元社員は、「購入のハードルを下げる真の狙いは、商品が必要かどうか考える時間を減らし、衝動的な購入を促すことよ」と語る。もしかすると現代人は、売り手側によって、少々欺かれすぎているのかもしれない。